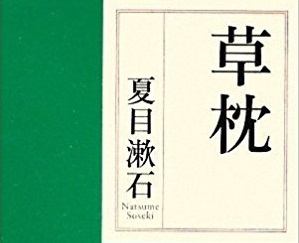久しぶりに読書録。パリ旅行のあいだに全く読書をする暇がなかったりして、そんなに長い作品では無いのですが、読み切るまで3週間も掛かってしまいました。
ということで、今回もAmazon Kindleで夏目漱石を。なんやかんやで、ドイツに来てから8作目の夏目漱石。
今回は1906年発表の中編(長編)小説、『草枕』を読みました。
先に感想を言ってしまうと、もう一度、伏線等に目をやりながらじっくり読み直したいなというのが正直なところ。表現が遠回しなので読んでいてぼーっとしてしまうのと、本を手に取る期間が空いてしまったりして、あまり記憶をしっかり保つことが出来なかったので。
そういうわけで、言い訳がましいですが、ずいぶん大雑把なまとめ方になるかと思います(毎度のことですが)。
あらすじ
ときは日露戦争のあった1905年前後。都会の喧騒に嫌気が差した画家が、山中の村に絵を描きに行く話。絵を描きに行くといっても結局この物語中に描くことは一度もなく、詩をしたためたりなんかして、悠々自適に滞在を楽しんでいます。
山村の宿で出会った女性・那美が主要な登場人物なんですが、彼女に主人公は肖像画を書くように頼まれます。一度は頼みを断るんですが、物語の一番最後では那美の上に表れている「憐れ」を目にし、「「それだ!それだ!それが出れば画になりますよ」」と那美に伝えます。そして、物語は終了。
最後まで読むことでこの「憐れ」が一つの主題だったことにようやく気がついたので、そこを振り返りながら、もう一度じっくりと読み返したいなと思うわけです。
夏目漱石の目に映る世界
大きな主題が明確に提示されるのは物語の最後ですが、それ以外の小さな部分にも、心に留まる個所が多々ありました。
例えば、詩人というものはどういうものなのか、文字にするとはどういうことなのか、という主人公の考察。このような考察がたくさん登場するんですが、そんな風に夏目漱石がもの見ていたのかと考えると、とても興味深かったです。
「こんな時にどうすれば詩的な立脚地りっきゃくちに帰れるかと云えば、おのれの感じ、そのものを、おのが前に据すえつけて、その感じから一歩退しりぞいて有体ありていに落ちついて、他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのである。詩人とは自分の屍骸しがいを、自分で解剖して、その病状を天下に発表する義務を有している。」「ちょっと涙をこぼす。この涙を十七字にする。するや否いなやうれしくなる。涙を十七字に纏まとめた時には、苦しみの涙は自分から遊離ゆうりして、おれは泣く事の出来る男だと云う嬉うれしさだけの自分になる。」
文字に表すことで自分を客体化し、感情をコントロールする。夏目漱石の持つ、詩に対する姿勢が見て取れます。
漱石の、画に対する考え方。少し長いですが引用します。
「この二種の製作家に主客しゅかく深浅の区別はあるかも知れぬが、明瞭なる外界の刺激を待って、始めて手を下すのは双方共同一である。されど今、わが描かんとする題目は、さほどに分明ぶんみょうなものではない。あらん限りの感覚を鼓舞こぶして、これを心外に物色したところで、方円の形、紅緑こうろくの色は無論、濃淡の陰、洪繊こうせんの線すじを見出しかねる。わが感じは外から来たのではない、たとい来たとしても、わが視界に横よこたわる、一定の景物でないから、これが源因げんいんだと指を挙あげて明らかに人に示す訳わけに行かぬ。あるものはただ心持ちである。この心持ちを、どうあらわしたら画になるだろう――否いやこの心持ちをいかなる具体を藉かりて、人の合点がてんするように髣髴ほうふつせしめ得るかが問題である。
普通の画は感じはなくても物さえあれば出来る。第二の画は物と感じと両立すればできる。第三に至っては存するものはただ心持ちだけであるから、画にするには是非共この心持ちに恰好かっこうなる対象を択えらばなければならん。しかるにこの対象は容易に出て来ない。出て来ても容易に纏まとまらない。纏っても自然界に存するものとは丸まるで趣おもむきを異ことにする場合がある。したがって普通の人から見れば画とは受け取れない。描えがいた当人も自然界の局部が再現したものとは認めておらん、ただ感興の上さした刻下の心持ちを幾分でも伝えて、多少の生命を※(「りっしんべん+淌のつくり」、第3水準1-84-54)※(「りっしんべん+兄」、第3水準1-84-45)しょうきょうしがたきムードに与うれば大成功と心得ている。古来からこの難事業に全然の績いさおしを収め得たる画工があるかないか知らぬ。ある点までこの流派りゅうはに指を染め得たるものを挙あぐれば、文与可ぶんよかの竹である。雲谷うんこく門下の山水である。下って大雅堂たいがどうの景色けいしょくである。蕪村ぶそんの人物である。泰西たいせいの画家に至っては、多く眼を具象ぐしょう世界に馳はせて、神往しんおうの気韻きいんに傾倒せぬ者が大多数を占めているから、この種の筆墨に物外ぶつがいの神韻しんいんを伝え得るものははたして幾人あるか知らぬ。」
「色、形、調子が出来て、自分の心が、ああここにいたなと、たちまち自己を認識するようにかかなければならない。生き別れをした吾子わがこを尋ね当てるため、六十余州を回国かいこくして、寝ねても寤さめても、忘れる間まがなかったある日、十字街頭にふと邂逅かいこうして、稲妻いなずまの遮さえぎるひまもなきうちに、あっ、ここにいた、と思うようにかかなければならない。それがむずかしい。この調子さえ出れば、人が見て何と云っても構わない。画でないと罵ののしられても恨うらみはない。」
小説の読み方についても、主人公の発言を通して漱石の考え方が現れていました。
「「勉強じゃありません。ただ机の上へ、こう開あけて、開いた所をいい加減に読んでるんです」
「それで面白いんですか」
「それが面白いんです」
「なぜ?」
「なぜって、小説なんか、そうして読む方が面白いです」
「よっぽど変っていらっしゃるのね」
「ええ、ちっと変ってます」
「初から読んじゃ、どうして悪るいでしょう」
「初から読まなけりゃならないとすると、しまいまで読まなけりゃならない訳になりましょう」
「妙な理窟りくつだ事。しまいまで読んだっていいじゃありませんか」
「無論わるくは、ありませんよ。筋を読む気なら、わたしだって、そうします」
「筋を読まなけりゃ何を読むんです。筋のほかに何か読むものがありますか」
余は、やはり女だなと思った。多少試験してやる気になる。
「あなたは小説が好きですか」
「私が?」と句を切った女は、あとから「そうですねえ」と判然はっきりしない返事をした。あまり好きでもなさそうだ。
「好きだか、嫌きらいだか自分にも解らないんじゃないですか」
「小説なんか読んだって、読まなくったって……」
と眼中にはまるで小説の存在を認めていない。
「それじゃ、初から読んだって、しまいから読んだって、いい加減な所をいい加減に読んだって、いい訳じゃありませんか。あなたのようにそう不思議がらないでもいいでしょう」」
「「なるほど面白そうね。じゃ、今あなたが読んでいらっしゃる所を、少し話してちょうだい。どんな面白い事が出てくるか伺いたいから」
「話しちゃ駄目です。画えだって話にしちゃ一文の価値ねうちもなくなるじゃありませんか」」
最後に、文明が個性を踏みつけようとしているのでは無いかという考え。
「いよいよ現実世界へ引きずり出された。汽車の見える所を現実世界と云う。汽車ほど二十世紀の文明を代表するものはあるまい。何百と云う人間を同じ箱へ詰めて轟ごうと通る。情なさけ容赦ようしゃはない。詰め込まれた人間は皆同程度の速力で、同一の停車場へとまってそうして、同様に蒸気の恩沢おんたくに浴さねばならぬ。人は汽車へ乗ると云う。余は積み込まれると云う。人は汽車で行くと云う。余は運搬されると云う。汽車ほど個性を軽蔑けいべつしたものはない。文明はあらゆる限りの手段をつくして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの方法によってこの個性を踏み付けようとする。一人前ひとりまえ何坪何合かの地面を与えて、この地面のうちでは寝るとも起きるとも勝手にせよと云うのが現今の文明である。同時にこの何坪何合の周囲に鉄柵てっさくを設けて、これよりさきへは一歩も出てはならぬぞと威嚇おどかすのが現今の文明である。何坪何合のうちで自由を擅ほしいままにしたものが、この鉄柵外にも自由を擅にしたくなるのは自然の勢いきおいである。憐あわれむべき文明の国民は日夜にこの鉄柵に噛かみついて咆哮ほうこうしている。」
このように随所随所で、漱石のものの見方が主人公の目線を通して描かれているのが読んでいてとても面白かったです。大きな主題を読んでいる最中に掴むことは出来ませんでしたが、改めて「憐れ」という主題を心において読み進めたら、これらの断片もまた違ったものに見えるのではないかと思います。
まとめ
ということで、夏目漱石『草枕』でした。読み切るまでに使った時間は3時間54分。長編と呼ぶには短めの本作でしたが、表現や単語が難しい部分もあったので、結構時間がかかった上に内容を明瞭に掴み切る事もできませんでした。ですので初めにも書いたように、また、主題を意識しながら読み返すことが出来たらなと思います。
では、最後までお付き合いいただきありがとうございました。