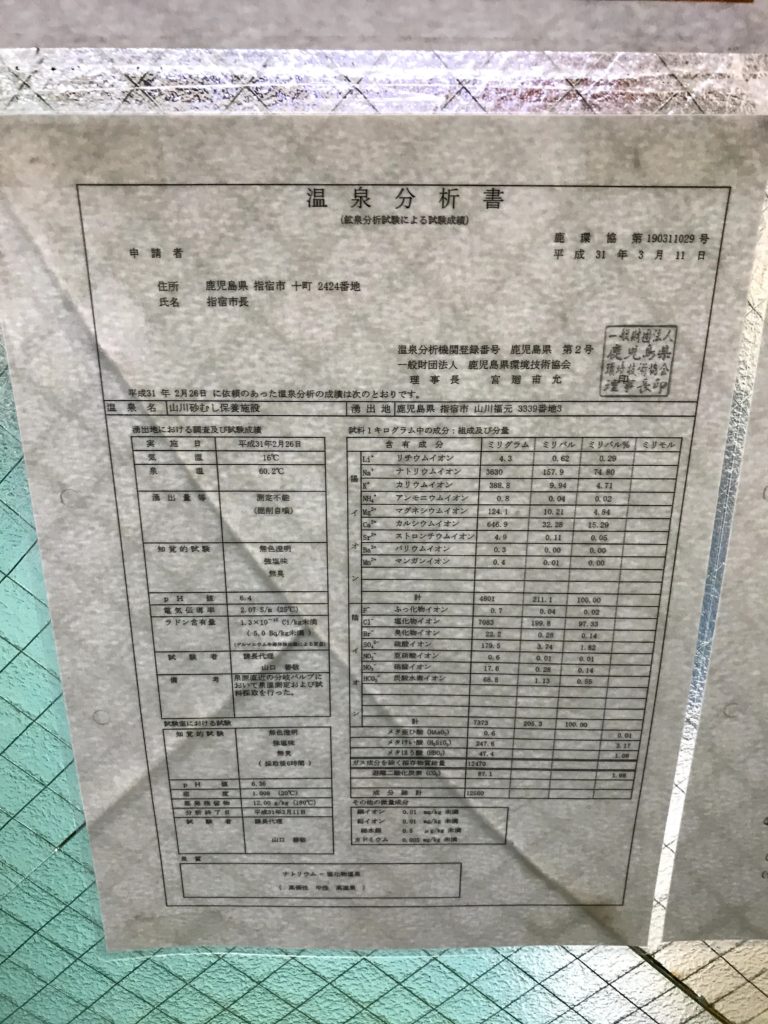いわゆる砂蒸し温泉には、過去何度か入ったことがある。
別府は竹瓦温泉と、指宿は砂蒸し会館の二ヶ所。
①海が近く②浅い地層が熱を持っており③湯も沸いてなければならない という条件を満たす土地はそう多く無く、全国を見渡してもそれほど数のない形態の湯である。
2014年に砂蒸し会館を訪れて以来、指宿への愛着はなかなかに強い。
ふるさと納税をしに探すのは、まず指宿。
砂蒸しの没入感を愛しはしているものの、訪問の希少さから、どうしても砂蒸し会館を繰り返し訪れてばかりであった。
東京に暮らしながら6年で3度の入湯は我ながらなかなかの偏愛ではなかろうか。
しかしこの度は、砂蒸し会館とは別の、山川の砂蒸しを味わってみようではないかと。
中韓からの訪日客頼みだったこともあり、客足は平時の1/5ほどとのことであった。
人の極端に少ない中で適正なコトを書けるやら随分とあやしいが、つらつらと書いてみる。
深みのある砂蒸し体験
“深み”という言葉に、人はどうしても頼りたくなってしまうものである。
何でもかでも、「深いですねえ」と一言加えておけばモノを分かったかのように振る舞った気になれるのが「深み」の一番の功罪であろう。
所属ゼミの笹原老師は、口ずっぱく”深み”に逃げてはならぬと学生に忠告しておられた。
そう言われても、(相対的に)深みのある体験をしたな、というのが感想。
ここでは”深み”のタネを見つける旅に出ることにする。
①湯へ向かう道程
少なからず”町”の雰囲気に佇む指宿駅からバスに揺られること30分。
風景からビルヂングはすっかり消え去り、海、山、野原の中をバスはゆく。
途中、山川の漁港やこじんまりとした造船所の脇を駆け抜けるのもまたよい。
町中にある砂蒸し会館では味わえない、道すがらでの経験である。
一時間に一本しかバスであるが、今回はツモりも良かった。
運転手さんは、タクシー上りと思しき饒舌な方。
路線バスの運転手がこれほどまでに親しみ深く、観光案内に熱心な光景には遭遇したことが無い。
「いやー、残念、今日は開聞岳は見えないですねえ」
「あの山は竹山なんですけれども、タイガーウッズが『スヌーピーが寝転がっているようだ』と言ったことからスヌーピー山とも呼ばれてます」
「この正面、海の向こうに見えるのが大隅半島です」
山川砂むし温泉前停留所での下車時にも、
「砂蒸しですか?ここで待ってればお迎えの車が来ますからね。あ、来てる来てる、ここで待ってれば大丈夫ですから」。
とにかく気さくに、景色に癒されると共に心温まる砂蒸しまでの道のりであったのでした。
②物理的な深さ
山川の砂蒸し「砂湯里」は、深い、物理的な意味で。
立地している海岸は周りを絶壁に囲まれており、かの有名な「たまて箱温泉」から見下ろされるような形になっている。
この息苦しさのない圧迫感が、どうも湯処での体験をより”深い”ものにしているように思われる。
平らな浜辺にすっと湯処が佇んでいたのでは、どうも味気がない。ただ海があれば良いというものではなくて、海を盛り立てる地形、空気があってこその海辺であろう。
その意味で湯処の裏に崖が切り立つこの環境は、海を愛でるにも湯を愉しむにも絶好の環境と言えるのではないだろうか。
③泥臭さの残る設備
決してボロ屋ではないが、海辺に屹立していることもあり、「砂湯里」の建物にはくすみが目立つ。それに、コンクリ打ちっぱなしの外壁もより施設の味わい深さを増している。
砂蒸し会館は大型のツアー客にも対応しているのだろうか、建物自体がフェリーターミナルのような、温かみはありつつも、手で撫でるとすっと滑ってしまうような、何というか掴みどころのない、”観光施設”のような空気を感じる。
一方こちら。
煙がもくもくと立ち上がる、この雰囲気である(蒸かし芋と共に)。
これを泥臭いと呼ぶのは失礼だという嫌いもあるが、それでも、やはり、いい意味で、泥臭い。
綺麗であることを疎むわけではないけれども、やはり染み付いた臭いというか、そういうものとの温泉の相性には敵わない。
④秘境感引き立つ地熱の妙
地熱の町、指宿。
もちろん指宿駅周辺や市街地にも地熱の源は脈々と這っているものと思われるが、それでも山川の、荒野は言い過ぎにしても、ざーっと広がる自然に感じる湯脈というのは街中のそれよりも格段に心地よい。
全く事実関係は知らないが、温泉近くには九州大学の地熱発電所があるらしく、それを聞くと「ここらが熱の強いところなんだろうなあ」と勝手に思考が強化される。
写真に収めていないので自分の記憶だけが頼りであるが、砂蒸し前にバス停に降り立った際の周囲の景色は、まるで原野にいるような、雲の低い天気も相まって、そんな気分であった。
市街が近く便利なのも悪く無いが、温泉は結局秘境に近づけば近くだけその味が深まるものなのである。
筆がのらずに放っていたら、恩納村のリゾートホテルで鹿児島の温泉について書き連ねるハメになってしまった。
心はすっかり蒼い海と燃える太陽に向いているが、それでもやはり、深く碧い海原に湯煙というのも、頭に描き直してみれば悪くないものである。